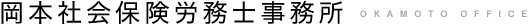カテゴリー:
-
精神疾患が疑われるが自覚がなく受診命令を拒否する従業員に対してとるべき措置
労務従業員のメンタルヘルス問題で近時の重要な問題の一つとして、職場において異常な言動が見られるなどして精神疾患が疑われるが、本人に自覚がない従業員に対してどのように対応するかという問題があります。従業員の異常な言動等により職場に悪影響が生じてい...
-
副業・兼業ガイドラインの改正に伴う副業・兼業の許容状況の開示対応のポイント
労務令和4年7月の2度目となる副業・兼業ガイドラインの改正では、法律によって義務付けられているものではありませんが、「副業・兼業の許容状況等の公表」が追加されました。公表すべき事項としては、まず、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付き許容...
-
身元保証契約の問題点と身元保証契約における機関保証事業者を利用するメリット
労務身元保証契約は、これまで、主に、企業が従業員を採用する際に身元保証書を従業員の親族や知人などから受領することにより締結されるのが一般的でした。身元保証契約を取り交すメリットは、企業側からすると、①従業員が問題行動を起こすことの抑止効果、②従...
-
定年後再雇用者の活用と有期雇用特別措置法の第二種計画認定の対象者
労務平成25年より「同一の使用者との有期雇用契約が5年を超えて繰り返し更新された場合に労働者の申し込みにより無期労働契約に転換するという労働契約法18条の無期転換ルールが施行されています。一方、同じく平成25年より始まった高年齢雇用確保措置によ...
-
試用期間中の問題社員を解雇するより、会社が訴訟リスクを避けて合意に基づく円満退職を選ぶ理由
労務問題社員には、「業務命令に従わない」「ミスを繰り返す」「いじめやハラスメントで周囲を退職させる」「金銭の不正」など様々なケースがあります。誤解が多いのは、試用期間中の従業員への対応です。試用期間中の従業員を解雇したことについて、従業員から不...