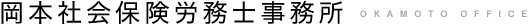カテゴリー:
-
2024年問題とドライバー不足を補うギグワーカーという働き方
働き方改革働き方改革が唱えられるずっと以前から正規雇用者の他に、さまざまな働き手がいます。パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員、派遣社員、フリーターといわれる人たち、それにフリーランスといった非正規雇用者です。これらの後発として加わったのが...
-
雇止め制限法理の適用による雇止めが有効か否かの判断方法とトラブル予防策
労務労働契約法第19条では、契約期間の定めがあっても、雇止めが制限される場合が規定されています。具体的には、有期社員が契約更新の申し込みを行った場合に、①雇止め法理が適用されるか、②雇止めに合理的理由があるかという2段階で審査されます。①雇止め...
-
企業が従業員にテレワークを命じる場合、従業員からテレワークを認めるよう求められる場合
就業規則会社の事情で、会社から従業員に対してテレワークを命じることがあります。テレワークには、通勤費の負担軽減などのメリットがありますが、他方で、自宅にテレワークに適した部屋がない等の理由で、従業員がテレワークができない場合があります。会社の都合で...
-
通勤手当の不正受給に際して企業が懲戒処分を検討する場合の対応
労務通勤経路が変更され、通勤手当の額が大幅に減額されていることになっていたはずなのに、これを申告せずに、余計に受け取っていたケース。そこでは、通勤手当の不正取得が疑われますが、その前提として、事実関係の確認が必要です。まず問題となるのは、従業員...
-
精神疾患が疑われる従業員への受診命令と受診を命じた場合の費用負担
就業規則仕事のミスが多くなり、身だしなみも言動も疑わしい従業員に会社がメンタル不調を心配し、医療機関への受診を勧め早めの対処を考えるケースがあります。会社が従業員に対し受診命令を行うことができるかは、就業規則に定めがある場合、健康管理上必要な事項に...