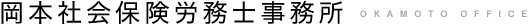カテゴリー:
-
パワハラ調査の判断に際しての留意点と相談者が納得しない場合の対応
労務パワハラ防止措置に関する法律(総合施策総合推進法)では、会社はパワハラの防止措置を講ずることが義務付けられ、相談者からの相談に適切に応ずることが求められます。会社は、現状を把握し相談者の意向を確認しつつ調査を開始し、最終的に事実認定をしたう...
-
テレワークを前提に採用した社員に出勤勤務を命じることの可否
労務使用者は、労働契約上当然に、従業員に対して配置換え(配転)を一方的に命じる権利、すなわち「配転命令権」を有するものではありません。従業員に対して配置換えを命じるためには、あくまで労働契約上、その権限が使用者側に設定されていることが必要です。...
-
裁量労働制適用者のテレワーク時の勤務時間についての指導・注意は具体的な指示に当たるか
労務裁量労働制とは、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要のある一定の業務について、法所定の手続きを経たうえでみなし労働時間数を定めた場合には、当該業務を遂行する労働者については、実際の労働時間数に関わりな...
-
取引き先の従業員からセクハラ行為を受けた場合の対応
労務均等法11条では、「職場において行われる性的な言動」に対して雇用管理上の措置を講じるよう事業主に義務づけています。すなわち、事業主に対しては、「自社内で」発生したセクハラに対応することを求めています。行為者と被害者がともに自社の従業員である...
-
私傷病休職満了時にリハビリ出勤を設けることの是非
人事・労務・給与リハビリ出勤とは、法令上、使用者に義務づけられているものではありませんが、私傷病休職者が通常業務に復職する前に、試し出勤を行ったり出勤後に軽易な作業を行ったりするなどして、復職後の業務に耐えられるかの見極めを行うために用いられるものです。実...